昨日の記事では「関西風桜餅」についてレポートしました。
そこで今回は「関東風桜餅」についてもう少し掘り下げてみようと思います。
実際に作製したわけではないので、画像はありません。
文字ばかりとなり読みにくいかもしてませんが、お付き合いください。
関西風は生地に道明寺粉と砂糖を使いましたが、関東風は白玉粉、餅粉、みじん粉、薄力粉、砂糖、白こしあんが生地の材料になります。
餅粉を使うのは何となく想像していましたが、白あんが入っているとは思いませんでした!
作り方を大雑把にまとめると、
・粉類と水、白あんを混ぜ合わせて生地を作る
・食用色素で焼く前の生地を着色する
・ホットプレートなどで生地を楕円形に広げて焼く
・皮の粗熱が取れたら餡玉を巻く
・桜の葉を巻く
蒸す工程が無いため、関西風よりも簡単に作れそうですね。
材料の「みじん粉」は「上南粉」とも呼ばれます。
道明寺粉と同じくもち米を蒸して乾燥したものです。
道明寺粉と異なるのは、乾燥後に粉砕し、色づかないように煎りあげている点です。
みじん粉に非常に近いものとして「いら粉」というものがあります。
いら粉よりも粒子が細かいのがみじん粉です。
また「寒梅粉」というものもあるのですが、これはもち米を蒸して搗き(つき)、お餅にしたものを焼いて粉にしたものです。
軽くてふわふわしており、水分を吸いやすいという特徴があります。
このように同じ原料でも製法によって色々な米粉が作られます。
それぞれの特徴や使い分けなどは実際に使ってみないと分からないのですが、いつか各種米粉を実際に使ってみて、その特徴の比較検証をするのが小さな目標です。


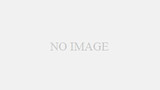
コメント