今回のテーマは「草餅」です。新緑の季節にぴったりのお菓子ですね(^^)
草餅というと思い浮かぶのは「よもぎ」ですが、実は元々は「ハハコグサ」が草餅に使われていたそうです。ハハコグサは春の七草の「ごぎょう」で知られていると思いますが、名前を聞いただけではどんな植物だったか思い浮かびませんでした…
なぜハハコグサからよもぎが使われるようになったかというと、「母子草」を餅に練り込むときに「母と子を突き合わせる」ということを連想させて縁起が悪いということから、よもぎが使われるようになったそうです。
今回の餅生地には上新粉と餅粉、そして上白糖を使います。
砂糖を加えることによって甘味が付くことはもちろん、砂糖の保水性によって生地が硬くなりにくくなる効果もあります。

生地をぬるま湯で練る時には、分量のぬるま湯を一度にすべて加えるのではなく約3/4を初めに加えてダマが無くなるまで混ぜます。その後残りのぬるま湯を加えて溶きのばすという2段階で水分を加えていきます。
これは粉末の濃度が高い状態の方が、ダマが逃げずにつぶれやすいためです。
良くココアを作る時に少量のお湯でココアを練ってから牛乳を加えるという作り方がパッケージに記載されていますね。これまでは、どうしてホットミルクにココアパウダーを加えるのだとダメなのだろうとぼんやりと考えていましたが、きっとダマを残さずつぶすためでしょうね。
(確かにホットミルクにココアパウダーを入れるとダマが大量にできるので、一生懸命スプーンの背でつぶしていました^^;)
教科書では冷凍よもぎが使われていましたが、今回は乾燥よもぎを使いました。
この乾燥よもぎ、実は地元に帰省した時に道端に自生しているものを摘んで茹で、乾燥させた自家製です。2年前に大量に作ったものを、今までずっと冷蔵庫で保存していました^_^;
本当は毎年収穫して更新していきたいのですが、なかなか消費できず今もまだ残っています。
これまではパンに練り込むくらいしかしてこなかったのですが、今はだしパックに詰めてお風呂に入れてみています。
さて、今回の餅生地は水分の多い柔らかい生地なので、さらしを2枚重ねで蒸しました。
よもぎは餅生地が蒸しあがる5分前くらいに、ラップに来るんだものを餅生地の隅に入れて殺菌も兼ねて加熱します。最初から生地と一緒に蒸してしまうと色が悪くなってしまうためです。


また、柔らかい生地は成形時に手に付きやすいという留意点もあります。そんな時はシロップを手に付けて成形するときれいにできます。
シロップは上白糖:水=1:2で混ぜたものですが、水を付けて成形するよりも傷みにくいという利点があります(砂糖によって水分活性が小さくなるためです)。
今回の形は「くわい」を表しています。くわいは「芽が出る」ということから縁起の良いものとされています。おせち料理にも入っていることが多いですね。

乾燥よもぎを使ったためか、それとも少しよもぎが足りなかったのか、お手本よりも緑が薄い仕上がりになってしまいました。
でも味はなかなか美味しかったです。やっぱり生地に砂糖が入っている方が好みだなあ (^^)


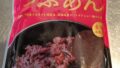
コメント